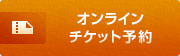セットリスト 公開!
M1.Delicious Breeze (塩谷哲)
M2.Ginza (塩谷哲)
M3.Beyond the Sea (小沼ようすけ)
M4.Fly Way (小沼ようすけ)
M5.Fellows (小沼ようすけ)
M6.Duoka guitar solo (小沼ようすけ)
M7.「無痛」メインテーマ piano solo (塩谷哲)
M8.Morning Bliss (塩谷哲)
M9.Summertime (ガーシュイン)
M10.Spain (チック・コリア)
M11.Spanish Waltz (塩谷哲)
《ENCORE》Jungle (小沼ようすけ)
2017/07/22 江戸川区総合文化センター 大ホール

塩谷哲さん インタビュー
―― 塩谷さんは子どもの頃、音楽教室に通われていたそうですが、そこで作曲や即興演奏を学ばれたのですか?
そうですね、即興演奏や簡単だけど曲を作ったりアレンジしたり、そういうことは日常的にしていました。その人の中にある音楽を表現するのが即興演奏だと思うんです。音楽教育の中でそういう機会を作っていくことが柔軟性を生むし、ひいては譜面に書かれた音楽に対しても自分の感性でコンタクトすることになる。子どもの頃にその経験ができたのはよかったですね。学問として作曲を勉強するきっかけにもなったし。
―― 芸大の作曲科ではオーケストラの曲を書いたりしていたんですよね。
そうですね、大学では専ら現代音楽ですが、その基礎となるのはやはりクラシックの作曲法なんです。幼少時からずっと曲を作ってはきたけど突然バッハやブラームスのような曲は絶対書けない。きっと学問としての確固たる作曲法があるに違いない、と。で、勉強して大学に入ってはみたけど、これはとんでもない世界だなと結局諦めちゃったわけですけど(笑)。その頃同時に、毎日のようにジャズのセッションもしていて、演奏して拍手をもらってっていう生の良さというか、表現が伝わることの方に喜びを感じてしまったんですよね。
だから、信じられないような音楽生活を送っていましたね。大学では誰も聴いてくれないような(笑)世界観の現代曲を作って、次の日にはオルケスタ・デ・ラ・ルスでサルサを弾いてみんなで踊り狂ってね、でその次の日には新宿のピットインで5人10人のお客さんの前でジャズを弾くという。
ジャズ、ラテン、現代音楽…、それぞれすごく好きで大事だった。でも、俺はいったいなんなんだ、と。全部中途半端じゃないかってコンプレックスが生まれたんです。それで、現代曲みたいな無調のラテンフィールの曲を作ってピットインで演奏する、といったことで自分を表現したりしていました(笑)。
―― そういうことができる人はなかなかいないのでは?
だからそれが自分なんじゃないか、って吹っ切れたんです。ジャズが好きで現代音楽も作曲してラテンも弾いて、という自分にしかできない音楽があるとすれば、それは本物かもしれないと思えた。長いこと、何を弾いても中途半端、本物じゃないよね、という感覚があったけれど、今は何を弾いても“その音楽を好きな自分が表現する”ということは本当で本物だと、そういう思いでやっています。ミュージシャンとしての根源的なアイデンティティですよね。
―― ジャズとのそもそもの出会いは?
親父がオスカー・ピーターソンが好きだったんです。親の田舎が秋田で、当時まだ東北自動車道なんてないから車で半日以上かけて家族で行く。その車中、ずーっとピーターソン(笑)。でも、やめてって言わなかったんですよ。ずっと聴いていたかった。スウィング感とかあのピアノの小気味よいリズムとか、とにかくピーターソンが僕のジャズの先生でした。
思えば不思議な音楽環境でしたね。姉のバレエの稽古場でかかっていたチャイコフスキーなんかを聴いて、こんな風にオーケストラのひとつひとつの楽器を知っていて作曲した人ってすごいな、と思ったり。でも親は僕を音楽家にしようなんて思ってなくて、趣味として人生の中にあれば楽しいでしょう、という感じでした。そんな環境で育つうちに、自然と音楽を好きになっていましたね。
―― いろんなジャンルを演奏される中で最近はジャズピアニストとしてご活躍ですが、ジャズに絞ろうと?
いえ、ジャズピアニストと自分で言うのははばかられるくらいで。実際ポップスの現場でもたくさん仕事させていただいていますし。僕が一番大事にしているのはリアリティなんです。ジャズの自由で柔軟で、という精神をもってポップスの現場でもピアノを弾くんです。僕がその曲に対して感じたものを表現すると、それをキャッチしてくれる人がいて、どんどんその曲の世界が広がっていく。柔軟であることがリアリティにつながっていくんです。
演奏家のパーソナリティや人生観、音楽観が感じられて、なおかつその曲を作った人の思いも感じられるときに、聴き手は感動するんだと思うんです。そこで演奏している人間そのものが音楽を通じて伝わる、そういう音楽家でありたいですね。いかにフラットな気持ちでリアリティをもって演奏できるか、それだけを考えています。
―― フラットな気持ちでいるのはなかなか難しいのでは?
難しいですよ。やっぱり人間だから、こう弾いたらどう思われるか、って考えたりね。
でもここ数年は、自分が手にしている音楽そのものが表現させてくれる、そういう感覚になってきました。そうなると、楽しいんですよね。いろんなものに感謝するようになるし。
最近小学校でアウトリーチのコンサートをやることがあるんです。誰も僕のことなんか知らない状況で、ピアノ1台で。そこでみんなの気持ちがつかめた実感があると、その状況すべてに感謝の気持ちがわきますね。それからいまNHKの「コレナンデ商会」という番組の音楽を担当しているんですが、全国の子供たちが自分の曲で歌って踊ってくれているということも心から嬉しいんです。伝わっているんだな、と。
―― 今回は小沼ようすけさんとのデュオですね。
彼もリアリティの塊みたいな男でね、本能的だし自然ですよね。人間がそうだから音も当然そうで、音楽自体もすごく大きなものを持っていて当然ジャズのスキルもすごくあって、その上での話かもしれないけれども。一緒にワイワイ食事したりお茶飲んだりしてるのと同じ状況で音楽ができるというか。ステージ上で集中力がありながらもすごくリラックスしている。理想的だと思います。彼がそういう風にさせてくれる。
曲を曲として演奏するんだけれども、毎日違った形でもいいし、でも今日はこんな感じだよねっていうのがお互い共通の感覚を持っていなければいけない。それを感じあいながら演奏する。だからイントロも毎回違ったりする。それは変えようねって言ってるんじゃなくてそうなっちゃう。
漫才みたいなものですかね。ネタは決まってるけど言い回しが違う、みたいな。
―― いろんな編成で演奏されていますが、デュオの魅力はどういうところでしょうか?
デュオは、相手の音をよく聴く、つまり相手を尊重しリスペクトしあうことが必要になってきます。その相手の音を聴くということが意外とできない、意識して訓練しないと。小曽根真さんとの共演によってそれがよくわかりました。彼は僕の弾いた音を全部弾けるんです。それくらい相手の音をよく聴いているしその能力がある。
このことはデュオに限った話ではありません。ビッグバンドのような大編成で全員が全員の音を聴き分けるのはかなり難しい。でもその意識をもって演奏していると、信じられないようなマジックが起こるんです。小曽根さんのNo name horsesなんかを聴くとそれがよくわかります。
どんなジャンルにしても一流の人たちに共通しているのは、まず共演者をリスペクトして、とにかく聴いているということ。それによって一緒に面白いものを作ろうよ、という前向きな姿勢ですよね。そういう充実した精神状態を皆が共有するということが、いい演奏を生むんだと思います。
―― 7月22日のコンサートも楽しみです。
絶対いいですよ!さっき言ったように彼がギタリストだから一緒にやるんじゃなくて小沼くんだから一緒にやるわけだから。そこを感じてもらえると嬉しい。
―― 本日はたくさんの貴重なお話をありがとうございました。